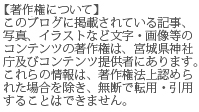村田町 白鳥神社 再生祈願祭
11月2日に御神木のイチョウが倒木の被害を受けた白鳥神社で、13・14日の2日間に亘って、『村田町名木を守る会』の協力のもと、御神木の再生祈願祭が執り行われました。

祭儀では、村田宮司による祈願ののち、氏子・総代の方々によって、
再生を願って新しい注連縄(しめなわ)か締め直されました。

今後は、東北大学、独立行政法人森林総合研究所の協力を得て、銀杏の木の保存・樹勢回復と次世代の神木となる苗木の育成に取り組むこととなりました。
研究所では、倒木を知った所員の方々が岩手県盛岡市の東北支所より駆けつけ、協力を申し出て下さったそうです。
また、樹齢1,000年以上ともいわれる御神木の年輪からは過去の大気の状況や気候を知る事ができ、貴重な研究資料になるとのことでした。
境内では、青空コンサートや即売会も開かれ、町内外から駆けつけた人々で賑わいをみせていました。